![]()
![]()
![]() 2014.10.15, 1999.2.1, 1998.2.15 (since 1997.8.1)
2014.10.15, 1999.2.1, 1998.2.15 (since 1997.8.1)
|
|
characters, base |
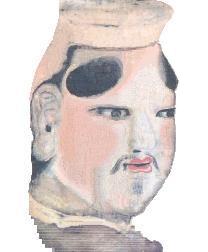
| ☆表示できない漢字について☆ 次の略字記号・借字記号で対応します。 | ||||
| □#(+△) | ・・・略字記号。□は略字、+△は部首追加。 | □$(-△) | ・・・借字記号。□は借字、-△は部首削除。 | |
| また、△部分は次の記号で部首の配置を示します。 | ||||
| ' | ・・・上部(かんむり) | " | ・・・上、左右部(かまえ) | |
| , | ・・・下部 | |||
| [ | ・・・右部(へん) | ] | ・・・左部(つくり) | |
●謎の祭神
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 温泉神社(筑紫国魂神社) おんせん、うんぜん (長崎県南高来郡小浜町、 加津佐町、 有家町) |
白日別 豊日別 建日別 速日別 豊久士比泥別 |
= = = = = |
四面宮と通称される。 九州九カ国の鎮守の神 |
| 草場神社 (行橋市) |
豊日別 | = | 豊日開国の祖 |
| 闇無浜神社(豊日別国魂神社) くらなしはま |
豊日別 | = | 崇神のとき |
| 八坂神社(闇無浜神社摂社) (大分県中津市) |
須佐之男 櫛名田姫 アマテラス八王子 |
=祭神 = =? |
|
| 大歳神社~国魂社 (大分県山国町守美) |
豊日別国魂 | = | 「山国町郷土誌叢書」国魂社は、 「豊前坊」と呼ばれ、 福岡の英彦山神宮の摂社、 「高住神社」のこととされる。 |
| 英彦山神宮~高住神社 | 天火明 | = | 「英彦山神宮史」、祭神は天火明 |
※ 古代、豊国は、現在の福岡県の一部と大分県。
●須佐之男の父
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 石上神宮(布留の社) (奈良県天理市布留町) |
布都御魂 | =素佐之男の父 | |
| 布都斯御魂 | =素佐之男 | ||
| 布留御魂 | =(主祭神) | ||
| 五十瓊敷入彦 | = | ||
| 宇摩志麻治 | = | ||
| 石上神社 (島根県平田市釜浦町) |
布都御魂 | = | |
| 石上神社 龍神社 (島根県平田市塩津町) |
布都御魂 大彦龍 大姫龍 |
= = = |
「神国島根」、旧称を宇美社と言い、延喜の制国幣小社に列せられ、 風土記に宇美社と記載されている神社は即ち今の石上神社のことである。 伊勢神宮御文庫蔵出雲国神名帳並びに神祇全書第一輯神名帳考証に、 共に「宇美神社、塩津村、海童」と銘記されている。 その他出雲風土記抄、出雲風土記解等にも詳しい。海童とも言う。 |
| 宇美神社 (島根県平田市平田町) |
布都御魂 | =素佐之男の父 | 「出雲国風土記」に記載あり。延喜の制国幣小社。 |
| 須崎神社 (名古屋市中区) |
布都御魂 須佐之男 |
=素佐之男の父 = |
|
| 総社神社 (茨城県石岡町) |
布留大神 | =素佐之男の子 | |
| 稲荷神社 (全国) |
宇迦御魂 | =素佐之男の第六子 | |
| 八坂神社 | 宇迦御魂 | =素佐之男の第六子 | |
==[仮説]==宇美神社は、布都御魂を素佐之男の父親として祀り、総社神社は布留を素佐之男の子として祀り、このことから、布都(素佐之男の父)と布留(須佐之男の子)の間の布都斯は、須佐之男の別名である。須佐之男がヤマタノオロチを斬った剣は、父親の剣を持ち出したもので、布都御魂の剣と呼ばれる。=={原田常治}==
●須佐之男
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 須賀神社 (島根県大原郡大東町須賀) |
須佐之男 すさのお 奇稲田姫 くしいなだひめ 八島野 やしまの |
八島野の正式名称は、清之湯山主三名狭漏彦八島野 すがのゆやまぬしみなさろひこやしまのと呼ばれる。 | |
| 須佐神社(須佐の大宮) (島根県簸川郡佐田町) |
須佐之男 稲田姫 足名槌 手名槌 |
= = =稲田姫、父 =稲田姫、母 |
|
| 古物神社 布留御魂神社 (福岡県鞍手郡鞍手町新北にぎた) |
須佐之男 | この地を布留毛能ふるもの村という。 「和名抄わみょうしょう」鞍手郡新分にぎた郷。 | |
| 金刀比羅宮 真須賀神社 (香川県仲多度郡琴平町) |
須佐之男 | =真須賀 | |
「古事記~須佐之男の大蛇退治」、
出雲国の肥河(斐伊川)の上の鳥髪に、老父と老女がいて、国津神で大山津見神の子で足名椎、妻は手名椎と名乗り、その女は櫛名田比賣と言った。・・・足名椎神を喚び「我が宮の首任となれ」と言い、「稲田宮主須賀之八耳神」と號(名付)けた。
==[仮説]== ?国狭槌は、足名槌・手名槌ゆかりの人物?====
●須佐之男の妃
稲田姫、父、足名槌あしなづち。母、手名槌てなづち。
「出雲風土記~飯石郡」、熊谷の郷。郡家の東北26里。古老が伝えて云うのに、久志伊奈大美しいなたみ等与麻奴良とよまぬら比売命、妊娠し産むときに、此処に到り来て、「甚だ久久麻麻志枳谷在り」という。故に熊谷という。
==[仮説]==須佐之男は、後世に「真須賀」と呼ばれる。稲田姫は等与麻奴良比売と呼ばれる。等与・麻奴良の比売で 須佐之男=麻奴良と考えられる。=={木屋}==1998.2.15
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 八重垣神社(佐久佐比古神社) (島根県松江市佐草町) |
素戔嗚 稲田姫 青幡佐久佐比古 |
=スサノオ = = |
スサノオと稲田姫が結ばれた。 |
| 稲田神社 (島根県仁多郡横田町稲田) |
稲田姫 | = | 稲田姫生誕地 |
※ 八重垣神社の壁画 宇多天皇の寛平5(893)年、出雲国庁を造営した際に、壁画が描かれた。巨勢金岡こせのかなおかの筆と伝えられる。須佐之男、稲田姫、アマテラス、市寸島姫、足名槌、手名槌の六神像が描かれる。
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 日御碕神社 (島根県簸川郡大社町日御碕) |
(神の宮、上の宮)須佐之男 |
=主祭神 |
「出雲風土記」美佐岐社。「延喜式神名帳」御碕神社。 社伝、素戔嗚尊は出雲の国造後、熊成峯に登り、鎮まる地を求め、柏葉を風で占うと、隠ヶ丘に止まった。御子の天葺根命は御魂をその地に奉斎した。(隠ヶ丘は社伝の裏にある。) |
| (日沈宮、下の宮)天照 | =大日霊女 | 社伝、天葺根命が文島にいると天照大神が降臨し奉斎した。(もと、文島(経島)に鎮座した。) | |
※ 日御碕神社はもともと岸壁に聳え立った素戔嗚尊の宮と、直下の経島ふみじまと呼ばれる小さな島にあった日沈宮と呼ばれる、天照大神の宮とに分かれていたのを、村上天皇の時代に勅命で名前を変え、現在のように崖上の小高い所に天照大神の宮を移したと言う。この日沈宮は、社伝によると、大和地方を中心に日の昇る方向が伊勢神宮で、日の沈む方向が日御碕神社にあたるからではないかと説明されている。苦しい説明である。ちなみに、日御碕神社周辺を宇迦と言う。
●須佐之男の子
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 若宮神社 (須我神社、境内) (島根県大原郡大東町須賀260) |
若宮 秋田 琴平 木山 稲荷 |
=八島野 =五十猛 =大歳 =磐坂彦 =宇迦御魂 |
須我神社の境内に若宮神社がある。 「由緒」若宮神社。秋田神社、金刀比羅神社、木山神社、稲荷神社を合祀。 須佐之男の五人の子(男子)が祀られている。 八島野は清之湯山主三名狭漏彦八島野という。 金刀比羅は琴平、宇迦御魂は倉稲魂ともいう。 |
| 八坂神社 (京都市東山区祇園町) |
八島茶見 五十猛 大屋津姫 抓津姫 大歳 宇迦御魂 大屋彦 須世理姫 |
=八島野 = = = = = =?磐坂彦 = |
八島茶見は「日本書紀」の名。 ==大屋彦は、磐坂彦の間違いか??== |
| 猛島たけしま神社(島原藩総社) (長崎県島原市宮町) |
五十猛 大屋津姫 抓津姫 |
= = = |
古くは森岳の地に鎮座。(森岳大明神) |
| 稲佐いなさ神社 (佐賀県杵島郡) |
五十猛 大屋津姫 |
= = |
|
| 韓国宇豆峯からくにうずみね神社 (鹿児島県国分市上井) |
五十猛 | =(祭神) | 航海と造林の守護神。 |
| 恵曇神社 (島根県八束郡鹿島町南) |
磐坂彦 | =須佐之男の御子 | |
| 三屋神社(御門屋神社) (島根県飯石郡三刀屋町給下) |
大己貴 稲田姫 |
= =?須世理姫 |
(母、稲田姫の手鏡) |
| 貴船きぶね神社 (大阪府交野市私市かたのしきさいち |
饒速日 | =(祭神) | 肩野物部氏の本拠地。 生駒山脈の北部、天野川の上流、巨石に囲まれた神社。 社伝に、神社名は天磐船からとられたとある。 |
| 大歳神社 | 大歳 | =大年 | 「延喜式神名帳」山城国乙訓郡、 大和国高市郡(二座)、 和泉国大鳥郡、 遠江国長上郡、 但馬国二方郡、 石見国那賀郡に七座が記載されている。 |
※ 須佐之男、大歳(後の饒速日)、五十猛を祀る八坂神社、貴船きぶね神社、大歳神社は、九州全土に分布している。
▼須佐之男の子
|
|
資料 | |
|---|---|---|
| (若宮)八島野やしまぬ、 八島茶見やしまつぬみ |
=清之湯山主三名狭漏彦八島野 すがのゆやまぬしみなさろひこやしまぬ 「粟鹿大明神元記あわがだいみょうじんもとつふみ」、 =蘇我能由夜麻奴斯弥那佐牟留比古夜斯麻斯奴 すがのゆやまぬしみなさむるひこやしましぬ |
|
| (秋田)五十猛 いたける |
=大屋彦 韓国宇豆峯神社(鹿児島県国分市) |
「伊太祁曾神社いたきそじんじゃ」(和歌山県和歌山市伊太祈曽558) 由緒=往古、日前国懸神宮の鎮座する秋月に鎮座したが、垂仁天皇16年、日前国懸神宮が名草浜より移動して来て、 社地を献上し、山東の地、亥の杜に遷座した。 |
| ( )大屋津姫 おおやつひめ |
「大屋都姫神社おおやつひめじんじゃ 」(和歌山県和歌山市宇田森59) 御祭=大屋都姫、左脇宮=五十猛命、右脇宮=抓都姫 | |
| ( )抓津姫 つまつひめ |
「都麻津姫神社つまつひめじんじゃ」 (和歌山県和歌山市吉礼911) 「続日本紀」、大宝2年(702年)2月22日条、 伊太祁曽・大屋都比売・都麻都比売3社を分遷した。 | |
| (金刀比羅)饒速日 にぎはやひ |
=大歳 | |
| (稲荷)宇迦御魂、倉稲魂 うがのみたたま |
=稲荷大明神として全国に祀られる。 | |
| (木山)磐坂彦 いわさかひこ |
||
| 須世理姫 すせりひめ |
末子相続。大己貴を養子に迎える。 三子、山代日子、木俣、武御名方。 |
須佐之男の第七子は、八坂神社には大屋彦とあるが、佐渡の度津神社に五十猛=大屋彦とある。
▼ 「出雲風土記」、須$佐能袁すさのをの御子2000.2.2
「出雲風土記」
意宇郡大草おおくさ郷 須$佐乎の御子、青幡佐久佐丁壮あをはたさくさひこ
大原郡城名樋きなひ山 須$佐能袁の御子、青幡佐草壮あをはたさくさひこ
島根郡山口郷 須$佐能袁の御子、都留支日子つるぎひこ
島根郡方結かたえ郷 須$佐袁の御子、国忍別くにおしわけ
秋鹿郡恵曇ゑとも郷 須$佐能乎の御子、磐坂日子いはさかひこ
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 恵曇神社(旧郷社) (島根県八束郡鹿島町南) |
磐坂彦 | =須佐之男の御子 | 祭神は須佐之男命の御子神。この地に到られし時、吾宮は此処に造らんと宣うた。 |
秋鹿郡多太ただ郷 須$佐能袁の御子、衝桙等乎与留比古つきほことをよるひこ
神門郡八野やの郷 須$佐能袁の御子、八野若日女やののわかひめ
神門郡古志こし郷 須$佐能袁の御子、和加須$世理比売わかすせりひめ
※ ↑須$(-[彡+[さんずい)
▼ 「古事記」、素戔嗚の子![]() 2014.08.01
2014.08.01
「古事記」の中で速須佐之男の神裔、および大国主の神裔について記した部分に、以前から疑問を感じていた。今回、この疑問を解明してみることにする。
従来の解釈では、大國主の王統譜は次のように推定できる。
■「大国主」王統譜[推定系図私案ver.0.3]2003.9.15,2001.03.05,1998.02.21
(推定系図私案共通尺度) ▼[大国主] ・ ・ ・ [磯城1神武]▼[磯城1神武] ・ ・ ・ ・ ▼[入10崇神] ・[足12景行] ・ ▼[別15応神] ・ ・
八島牟遲能神━━━鳥耳━━━┓ ・ ・ ・
◆◆ ┃ ・ 葦那陀迦━━┓ ・ ・
淤迦美━━━━━━日河比賣━━━━━┓天之都度閇知泥━┓ 刺國大神━━━━刺國若比賣━━┓ ┃ ・ (八河江比賣)┃ ・
おかみ ひかはひめ ┃あめのどへちね ┃ ・ さしくにわかひめ┃ ・ ┃ ・ ┃ ━淤加美━━━━━━比那良志毘賣┓ 敷山主━━━青沼馬沼押比賣┓ 天狹霧━━━━━━遠津待根━━━┓
{0} {1} {2} ┃ {3} ┃ {4} {5} ┃ {6} ┃ {7} {8} ┃ {9} {10} ┃ {11} {12} ┃ {13} {14} ┃ {15}
>━速須佐之男━┳八島士奴美①━┳━布波能母遲久奴須奴┻深淵之水夜禮花━┻━淤美豆奴━━┳┳天冬衣━━━━┻━大國主・・┻━━鳥鳴海━━━┳━國忍富━━━┻━速甕多気佐波夜遲奴美┳甕主日子━━┻━━多比理岐志麻流美┳美呂浪━━━━┻━布忍富鳥鳴海┳━━天日腹大科度美┻━━遠津山岬多良斯
┃やしまじぬみ ┃ ふはのもぢくぬすぬ ふかぶちの おみづぬ ┃┃あめのふゆぎぬ ◆ ◆ ┃ ◆ ◆ ・ ┃ ┃ ◆ ◆┃
櫛名田比賣━┛清之湯山主 ┃ みずやれはな 八束水臣津野┃┃天之葺根 日名照額田毘道男伊許知邇┛ 天之甕主━━━━━━前玉比賣━━━━┛比比羅木其花麻豆美━活玉前玉比賣━┛ 若盡女━━━┛
くしなだひめ 三名狭漏彦 ┃ やつかみづおみ┃┃
八嶋篠 ┃ づの┃┗赤衾伊努意保須#美比古佐倭気━━┳
・ ┃ ┃ あかぶすまいぬおおすみひこさわけ┃
┃ ┃ ┃
大山津見━━━木花知流比賣━┛ 布怒豆怒━━━━━━布帝耳━━━┛ 天瓺$(偏と旁が逆)津日女━━━┛
ふのづの ふてみみ 天甕津日女
阿麻乃弥加津比女
>━速須佐之男┳┳大年神
┃┃おほとし
神大市比賣━┛┗宇迦之御魂神
かむおほいちひめ うかのみたま
さて、再度、古事記の次の記事を再検討してみる。
|
★「古事記~速須佐之男の大蛇退治」 |
※ 鋤$(-力){鉏}
従来(推定系図私案ver.0.1~ver0.3)、「古事記」のこの部分において、例1「Aの神、・・・を娶り生める子は、B。この神、・・・を娶り生める子は、C。」は、例2「B(名詞)。この神、・・・を娶り生める子は、C。」と同様に「この神」=「B」と訳してきた。この結果、「右にあげた八島士奴美神よりしも、遠津山岬多良斯(帯)までを十七世」は直系で17世代と書かれているが[推定系図私案ver0.3]にあるように15世代の誤記とうけとめていた。
今回、例1「Aの神、・・・を娶り生める子は、B。この神、・・・を娶り生める子は、C。」の「この神」は、本来「Aの神、・・・を娶り生める子は、B。」の文章の主語(A)を受けるべきであると言う結論に達した。その結果[推定系図私案ver0.4]が得られた。また、八島士奴美神から遠津山岬帯まで高比賣を除いた十七柱となる。「古事記」は大国主王統譜が十七世続いたように見せかけていることになる。
■「大国主」系譜[推定系図私案ver.0.1]2014.08.01
(推定系図私案共通尺度) ▼[大国主] ・ ・ ・ [磯城1神武]▼[磯城1神武] ・ ・ ・ ・ ▼[入10崇神] ・[足12景行] ・ ▼[別15応神] ・ ・
>━速須佐之男━━━┓
┣━①八島士奴美━━━┳━②布波能母遲久奴須奴
┃ やしまじぬみ ┃ ふはのもぢくぬすぬ
櫛名田比賣━━━┛ 清之湯山主 ┃
くしなだひめ ┃ 三名狭漏彦 ┃
┃ 八嶋篠 ┃
大山津見━━━━━━木花知流比賣━━━┛
┃ ┣━③深淵之水夜禮花
┃ ┃ ふかぶちの
┃ ┃ みずやれはな
淤迦美━━━━━━━日河比賣━━━━━┛
おかみ ┃ ひかはひめ
┃ ┣━④淤美豆奴━━━赤衾伊努意保須#美比古佐倭気━┳
┃ ┃ おみづぬ あかぶすまいぬおおすみひこさわけ┃
┃ 天之都度閇知泥━━┛ 八束水臣津野 天瓺$(偏と旁が逆)津日女━━┛
┃ あめのどへちね やつかみづおみ 天甕津日女
┃ ┃ づの 阿麻乃弥加津比女
┃ ┣━⑤天冬衣
┃ ┃ あめのふゆぎぬ
布怒豆怒━━━━━━布帝耳━━━━━━┛ 天之葺根
ふのづの ┃ ふてみみ ┃
┃ ┣━⑥大國主━━━━┳━⑦阿遅須枳高日子━━━┳多伎都比古
刺國大神━━━━━━刺國若比賣━━━━┛ 大穴牟遲 ┃ 阿遲鋤$(鉏)高日子根┃(石神)
┃ さしくにわかひめ おほなむぢ ┃ 迦毛大御神 ┃[楯縫郡]
┃ 葦原色許男 ┃ [意宇郡] ┃
┃ あしはらしこを┃ 天御梶日女━━━━━━┛
┃ 八千矛 ┃
┃ やちほこ ┣━高比賣(下光比賣)
┃ 宇都志國玉 ┃
┃ うつしくにだま┃
┃ 多紀理毘賣━━━┛
┃ ┣━⑧事代主
┃ 神屋盾比売━━━┛
┃ ┣━⑨鳥鳴海
┃ 八島牟遲能神━━━━━鳥耳━━━━━━┛ ◆ ◆
┃ ◆◆ ┣━⑩國忍富
┃ 日名照額田毘道男┛ ◆ ◆
┃ 伊許知邇┣━⑪速甕多気佐波夜遲奴美
┃ 葦那陀迦━━━━┛
┃ (八河江比賣) ┃
┃ ┣━⑫甕主日子
┃ 天之甕主━━━━━━━前玉比賣━━━━┛
┃ ┣━⑬多比理岐志麻流美
┃ 淤加美━━━━━━━━比那良志毘賣━━┛
┃ ┣━⑭美呂浪
┃ 比比羅木其花麻豆美━━活玉前玉比賣━━┛
┃ ┣━⑮布忍富鳥鳴海
┃ 敷山主━━━━━━━━青沼馬沼押比賣━┛
┃ ┣━⑯天日腹大科度美
┃ 若盡女━━━━━┛
┃ ┣━⑰遠津山岬多良斯
┃ 天狹霧━━━━━━━━遠津待根━━━━┛
┃
┣━大年神
┃ おほとし
┃
┣━宇迦之御魂神
>━大山津見━━━━神大市比賣━━━┛ うかのみたま
かむおほいちひめ
[推定系図私案ver.0.4]2014.08.01,2003.9.15,2001.03.05,1998.02.21
>━大穴牟遲━━━━┳壮夫
┃
八上比賣━━━━┛
>━葦原色許男━━━┳
┃
>━速須佐之男━━━━━━須勢理毘賣━━━┛
>━八千矛━━━━━┳御穂須〃美
┃
意支都久辰為━━━━俾都久辰為━━━━━━沼河比賣━━━━┛
■葦原中国(2001.3.30)
| 大国主 | 資料 | |
|---|---|---|
| 01八島士奴美 | 「古事記~須佐之男の大蛇退治」、出雲国の肥河(斐伊川)の上の鳥髪に、老父と老女がいて、国津神で大山津見神の子で足名椎、妻は手名椎と名乗り、その女は櫛名田比賣と言った。・・・足名椎神を喚び「我が宮の首任となれ」と言て、稲田宮主須賀之八耳神と號をさづけた。 「先代舊事本紀~地祗本紀」素戔鳥尊、将に婚処をもとめ、清地に到り「須賀須賀斯」という。其の地より雲が立ち上る。歌を作って言うには やくもたついづもやえがきつまごめにやえがきつくるそのやえがきは 生まれた児は大己貴神。亦の名、八嶋士奴美神。亦の名、大国主神。亦の名、清之湯山主すがのゆやまぬし三名狭漏彦みなさるひこ八嶋篠やしましの。亦の名、清之繋名すがのゆいな坂軽彦さかかるひこ八島手やしまで命。 「出雲国風土記~意宇郡」屋代やしろ郷・・・・天乃夫比命の |
|
| 02布波能母遲久奴須奴 | 「古事記」この神、大山津見の女、木花知流比賣を娶る。布波能母遲久奴須奴を生む。 御伴に、天降り来た社は、印支(稲置)等の遠つ神、天津子命が「吾が静まり坐そうと志す社」と詔した。故に社という。神亀3年、字を屋代と改める。 | |
| 03深淵之水夜禮花 | 「古事記」布波能母遲久奴須奴、淤迦美の女、日河比賣を娶る。深淵之水夜禮花を生む。 「古事記」出雲臣は天之菩卑能命の御子建比良鳥命から出た。 「日本書紀」高皇産日尊、八十諸神を召し集め、問いて曰わく、「吾、葦原中国の邪鬼を撥ね平らげむと欲す。・・・・天穂日命、是神の傑いさをなり。試そう。」といった。然れども此の神、大己貴神に佞り媚びて、3年たっても尚、報い聞けず。其の子、大背飯三熊之大人うし、亦の名、武三熊之大人を遣わす。此亦、その父に順じて報い聞けず。 | |
| 04淤美豆奴 | 「古事記」この神、、天之都度閇知泥を娶る。 | |
| 05天冬衣 | 「古事記」淤美豆奴、布怒豆怒の女、布帝耳を娶る。天冬衣を生む。 「出雲国風土記~意宇おう郡」国引き坐す八束水臣津野やつかみづおみづの命、詔りたまいて、「八雲立つ出雲の国は、狭布の雅国であり、初国は小さく作られた。 「出雲国風土記~出雲郡」杵築きづき郷・・・・八束水臣津野命の国引き給う後に、天の下所造らしし大神の宮奉るため、諸の皇神等、宮処に参い集いて杵築いた。故に寸付きづきという。 「出雲国風土記~出雲郡」伊努郷意美豆努の御子、赤衾伊努意保須#美比古佐倭気。 「出雲国風土記~島根郡」島根と号する所以は、国引き坐す八束水臣津野命の詔りたまいて名を負せ給う。 「出雲国風土記~神門郡」神門の水海。・・・即ち水海と大海との間に山在り。此は意美豆努命の国引き坐す時の綱なり。 | |
| 06大國主 | 「古事記」刺國大神の女、刺國若比賣を娶る。大國主を生む。 「出雲国風土記~出雲郡」伊努郷。国引き坐しし意美豆努命の御子、赤衾伊努意保須美比古佐倭気能あかふすまいぬおおすみひこさわけの命の社、即ち郷の中に坐す。 「日本書紀~神代上」[第四の一書]素戔嗚尊、其の子、五十猛神を帥いて新羅国に降り到り、曾尸茂梨の処に居ます。......遂に埴土を以て舟を作って、東に渡って出雲の簸の川上の所に在る、鳥上の峯に到った。時に其処に、人を呑む大蛇が有った。素戔嗚尊、乃ち『天蠅斫剣』を以て、彼の大蛇を斬る。時に蛇の尾を斬ると刃が欠けた。即ちさいて視ると、尾の中に一つの神剣が有った。素戔嗚尊がいうのに「此れは吾が私に用いてはならぬ。」といって、乃ち五世の孫天之葺根神を遣わして天に上奉した。此れは、今、所謂、『草薙剣』である。 | |
| 「出雲国風土記~出雲郡」杵築郷。・・・・八束水臣津野命が国引き給う後、天の下所造らしし大神の宮を奉ろうと諸々の皇神等、宮処に参集して杵築いた。故に寸付と云う。神亀3(726)年、字を杵築と改める。 |
▼ 「秀真伝ほつまつたえ」、素戔嗚の子1998.2.15
>━素戔嗚━┳┳大屋彦
そさのを┃┃おおやひこ
櫛稲田姫━┛┣大屋姫
くしいなだひめ┃おおやひめ
┣妻津姫
┃つまつひめ
┣事八十
┃ことやそ
┣津軽大本
┃つがるうもと
┣大年倉結
┃おおとしくらむすび
┣葛城一言主
┃かつらぎひとことぬし
┗酢芹姫
すせりひめ
※ 葛城一言主
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 射矢止いやと神社 (和歌山市) |
一言主 天香語山 |
「紀の国のおみや」由緒書、天香語山、一言主は神代のむかし、 五十猛と共に本国に天降り、・・・ | |
| 葛木一言主神社 (御所市森脇) |
一言主大神 | ||
「古事記~雄略」、吾は悪事も一言、善事も一言、言離之神ことさかのかみ、葛城一言主の大神である。
※ 津軽大本
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 志多備したび神社 (島根県八雲村) |
「伝承」聖神社、速玉男。大元神社、事解男。 | ||
| 大元神社 (福島県三春) |
江戸時代、秋田氏の移住地。 「東日流六郡誌大要」、豊後の宇佐郷御許山に由来する。 | ||
●八島野やしまぬ
=清之湯山主三名狭漏彦八島野
すがのゆやまぬしみなさろひこやしまぬ
「粟鹿大明神元記あわがだいみょうじんもとつふみ」、
=蘇我能由夜麻奴斯弥那佐牟留比古夜斯麻斯奴
すがのゆやまぬしみなさむるひこやしましぬ
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 素鵝社(出雲大社の摂社) | 須佐男(素戔嗚) | ||
▼ そが、すが
素鵝=須賀=宗我=蘇我
●大屋津姫おおやつひめ・抓津姫つまつひめ(UP1998.2.25)
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 天健金草あまたけかなかや神社 (島根県隠岐郡都万村) |
大屋津媛 抓津媛 誉田別 |
隠岐、島後の都万村、大屋津姫、抓津姫の姉妹を祀る。 「隠州越智郡都萬院正八幡宮之縁起」、木種を植えて 国土開発に尽くされた姉妹は当地に来られ、 農耕を指導し民を教化された。 太古は、抓津姫のおられた狭山の湧水、 大屋津姫の住まわれた大屋の仙洞を そのまま姉妹の来られた神域として奉斎していたが、 その後、いつ頃にか、社殿を造営して二女神を鎮斎し、 天建金草と称した。 | |
| 大屋姫命神社 (島根県大田市大屋町) |
大屋姫 | 「神国島根」大屋姫命は須佐之男命の息女としてこの地に住み大屋郷と名づけられ、周辺の造林開拓にあたったと古老が伝えた。 | |
| 妻山つまやま神社 (佐賀県杵島郡白石町馬洗) |
抓津姫 抓津彦 |
郷土の繁栄をもたらし、国土開発に功顕された産土神であり、 我が遠い祖先の氏神である。 | |
==仮説==(1998.2.25)かつて、有明海に望む地域(佐賀県杵島郡)に都万の国があった。==[木屋]==
●宇迦御魂うがのみたま、倉稲魂くらいねたま
稲荷大明神として全国に祀られる。九州や東海地方では、倉稲魂くらいねたまとしている神社も多い。
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 伏見稲荷大社 ふしみ (京都市伏見区深草藪之内町) |
宇迦之御魂大神 佐田彦大神 大宮能売大神 田中大神 四大神 |
秦氏一族が禰宜となる。 稲荷神社総本山。五柱を稲荷大明神と称す。 宇迦之御魂大神(下社・中央座)佐田彦大神(中社・北座) 大宮能売大神(上社・南座)田中大神(田中社・最北座) 四大神(四大神社・最南座) | |
●須世理姫すせりひめ
| 神社名 | 祭神 | 資料 | |
|---|---|---|---|
| 出雲大社いずものおおやしろ(杵築大社) (島根県簸川郡大社町杵築) |
大国主(中央) 須世理姫(右) 多紀理姫(左) |
= =出雲 =日向 |
|
| 三屋神社 (島根県飯石郡三刀屋町給下) |
大国主 稲田姫 |
= =須世理姫の間違い? |
「稲田姫の手鏡」がある。 「出雲風土記」、御門屋みとや社。 裏山の「高丸山」には出雲族のものと思われる 前方後方墳がある。女性の古墳とみられる。 「漢式六獣鏡」出土。 |
須世理姫の母、稲田姫に置き換えられている。
大国主との間に三子、山代日子やましろひこ、木俣きまた、武御名方たてみなかたがあった。
Reference:]
「出雲風土記」
「古事記」
消された覇王~伝承が語るスサノオとニギハヤヒ、小椋一様、河出書房新社、1988.10.28
記紀以前の資料による古代日本正史、原田常治、同志社、1976.9.27